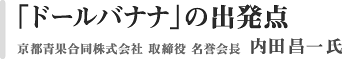バナナの立役者たち
バナナの知られざるストーリー
![]()
昭和6(1931)年、京都府生まれ。昭和29(1954)年、同志社大学経済学部卒業後、昭和30(1955)年、京都青果合同株式会社へ入社。昭和50(1975)年に同社代表取締役社長(現:取締役名誉会長)、株式会社京果食品代表取締役会長(現:名誉会長)に就任。平成3(1991)年に株式会社京都総合食品センター代表取締役社長、平成9(1997)年に株式会社ローヤル代表取締役会長兼社長(現:名誉会長)に就任。食糧問題や流通問題、食の安全性、食育などに造詣が深い。京都商工会議所副会頭、京都経済同友会代表幹事、京都府農政問題協議会委員、京都市中央卸売市場協会会長も務めた経歴の他、財団法人京都市体育協会会長、京都府ソフトテニス連盟会長なども務める。
小さい頃、両親が商売をしていて、私も朝6時頃からたたき起こされて店の手伝いをしていました。
父はバナナ加工の名匠で、当時は都市ガスを使ってバナナの色付けをしていました。
籠[かご]に入っている台湾からのバナナを、コンロの上にレンガを一つ置いて都市ガスを点けるのですが、
ガス中毒にかかることもあり、大変危険な作業環境でした。
父も、ガスの爆発事故により大やけどを負ったことがあります。
それから、蒸し暑い夏の日は、夜中であっても近所の氷屋さんから氷を持って来てもらい、
水をざーっと撒き、そうして、暑さでバナナが柔らかくなるのを防いでいたのです。
戦後、1年以上経ってからでしょうか、バナナが日本に入ってきました。
ある日父が、貴重で高価だったバナナを1本くれたのです。
当時中学3年生だった私は、学校へ持って行って「これがバナナだぞ!」と、
同級生に薄く切ってふるまったこともありました。
昭和25(1950)年の民間貿易の再開以降、多くの業者がバナナ事業に参入しました。
昭和23(1948)年に、私の伯父が青果卸売会社の京都青果合同を設立し、
神戸港などで輸入業者から購入したバナナを室[むろ]で熟成加工して販売していました。
私は昭和30(1955)年に京都青果合同へ入社したのですが、
卸売業だけでなく輸入事業に乗り出し、バナナの栽培が盛んだった台湾へ行きました。
農場視察をした私はバナナ事業に大きな手ごたえを感じ、帰国後、社長に事業拡大を強く進言。
社内に貿易部をつくり、バナナの輸入事業に積極的に取り組んだのです。
当時は台湾のほか、エクアドルなど南米からもバナナが入ってきていました。
輸入自由化以降、日本のバナナ市場には台湾だけでなく、
より安定して調達できるアジアの生産拠点が必要だと感じ、
私はほかの青果会社の方々とマレーシアやフィリピンなど海外視察へ行きました。
中国・広東省産のバナナを輸入したこともありますが、水分の多い土手で作られていたからか、
輸送途中に柔らかくなりすぎてしまったという失敗もありました。
新しいバナナの産地としてフィリピンに着目したのは、昭和40(1965)年頃のことです。
数カ国を視察した結果、広大な土地でバナナが栽培されていたこと、
労働力が確保できることから、フィリピンが最適地だと感じました。
その後、伊藤忠商事の宇坪正隆氏とフィリピンでのバナナ事業を進めるべく、
昭和41(1966)年、私と宇坪氏はキャッスル&クック社(現:ドール)のグループであった
スタンダード・フルーツ社のスミス副社長に現地でお会いし、
フィリピンでのバナナ事業を視野に入れた現地視察をしました。
セスナ機から眺めた見渡す限りのバナナ畑は、今でも忘れられない光景です。
その後、強い期待感を持って、ドールと伊藤忠商事による「伊藤忠ドール」の時代が幕を開けました。
余談ですが、スミス副社長と訪れたフィリピン・ミンダナオ島のイホ・プランテーションでは、
バナナが根腐れを起こしていました。しかし副社長は驚きもせず、にこにこしていたのです。
経験のある現地の作業者たちが、根腐れの対処法などを心得ていたため、
心配に及ばないということがわかっていたのでしょうね。
-

- 昭和41(1966)年、フィリピンのイホ・プランテーション視察時の集合写真(右から2番目がスミス副社長、左から2番目が宇坪正隆氏、右が内田昌一氏)
-

- フィリピン・ミンダナオ島のバナナプランテーション風景
こうしてフィリピン産バナナの輸入が始まったのですが、
特に大変だったのは価格交渉です。
毎年、1年間の契約更新をするのですが、
そのような商売の仕方は私たちにとって初めての経験でしたので、
毎年、毎回、交渉の際には最後の最後まで白熱した議論が交わされました。
私も「伊藤忠青果協議会」の幹部として価格交渉に臨むなど奔走しました。
日本人は義理人情に厚く、相手に損をさせてはいけない、
自分がぼろもうけをしてもいけないという商売感覚があります。
スタンダード・フルーツ社も、東洋的というか日本人的な感覚を持ち合わせていて、
いつも私たちと同じ土俵に立ってものを考えていました。
だからこそ伊藤忠ドール時代は長く続き、発展していったといえるのでしょうね。
-

- カートンに入ったバナナを船積みしている様子
-
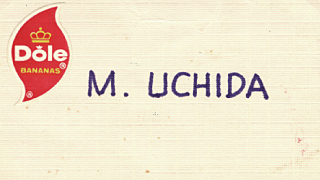
- 内田昌一氏のネームカードには、ドールの旧ロゴのシールが
-

- 昭和43(1968)年、ニューオーリンズの
スタンダード・フルーツ社の前で(中央が内田昌一氏)
ドールは業界に先駆けた数々の改革とともに、今日に至る事業発展を遂げてきました。
最近発売された主力商品の「極撰」は素晴らしい味を持つバナナです。
「本当においしいバナナ」とは、昔の台湾バナナのような粘りがあり、
香り高いバナナだと考えていますが、「極撰」は限りなくそれに近い味を表現しています。
私が幼少の頃から親しんだ味に近いのです。
私には、夢があります。それは、昔ながらのレンガとガスコンロによる色付けで加工した、
理想的なバナナをつくりたいと思っているのです。
父がつくっていたような、粘り気のある甘いバナナに、日数をかけてじっくり仕上げていく。
この夢は近いうちに実現させたいですね。
そしてドールには、消費者のさまざまな好みに応えられる商品を展開していってもらいたい。
例えば、「極撰」をシリーズ展開し、より粘り気のある高地栽培バナナを開発してもよいでしょうし。
これからも消費者が「おいしい」と思うバナナを、どんどん提供してほしいと期待しています。
-

- ドールの「極撰」
バナナはその国の文化をはかるバロメーターである、と昔からよくいわれていました。
ベルリンの壁が崩壊した当時、東ベルリンの人々は西へ流れ込み、
バナナを買いあさっていたそうです。
栄養価が高く、衛生的にも優れているため、今回の東日本大震災でも、
京都青果合同はすぐに被災地にバナナを持って行きました。
安くて手に入りやすく、いざという非常時にとても役立つバナナは、
「たかがバナナ、されどバナナ」ですよね。
消費量の面でもバナナは“果物の王様”ですから、
「バナナを大切にせなあかんで!」という言葉は、私の口癖になっているのです。